土と脂 -微生物が回すフードシステム
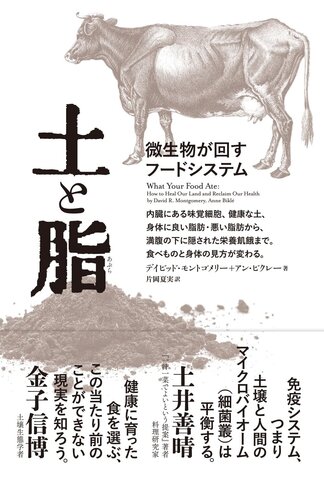
-思いを受け止めて-
一見別物に見える「土と脂」に惹かれて手に取ってみようと思う人はいるに違いない。植物根圏のどのような微生物が植物の生育や病害虫、高温、乾燥ストレスへの耐性に結び付いているのか、科学者は解明しようと切磋琢磨している。本書の出版はタイムリーだと言えよう。しかし、土壌微生物を菌根菌とその他の細菌に大雑把に分け、糸状菌や放線菌等の微生物と植物との共生関係などに触れないのはいささか乱暴だ。除草剤は雑草作業を省力化する大切な手段であるので、簡単には切り捨てられない。農薬は急性毒性、慢性毒性、発がん性、アレルギー等皮膚感作性、繁殖性などの安全性試験を課したうえで、厳しく残留基準を守り使用されている。病害虫のみならず、ヒトも含めて動物も植物の敵である。それゆえ、植物は「天然農薬」をファイトケミカルとしてつくっている。ファイトケミカルに農薬と同じく厳しい安全性試験を課すとどうなるか。相当な数の物質が試験に引っ掛かることになるであろう。私たちはそれらのやっかいな物質も含めて「風味」を感じているのである。
カバークロップを用いて輪作を行い土壌の有機物や微量元素を保とうとするのは良い考えだ。輪作は連作障害を防ぐ。だが不耕起・無農薬栽培が可能な条件は限られており、全世界でそれを実践すると、富裕層しか買えない農作物が店頭にならぶことになるであろう。いや、下手をすると、店頭から農作物が姿を消すかもしれない。本書では「農芸化学」も否定されている。農芸化学の「芸」はもともと「藝」で、手を加えて植物を育てることを意味する。転じて、日本農芸化学会では農学における化学分野にとどまらず、発酵、栄養、健康など広範囲の分野で活発に研究が行われている。日本農芸化学会のウエブサイトをご覧いただきたい。
このように前のめりの前半とはうって変わり、正しい科学的根拠をもとに私たちの健康維持にオメガ3とオメガ6の脂肪酸のバランスが大切であると主張している11章以降は、すっと読み終えることができた。最後の結論は比較的おだやかである。2名の著者が前半と後半を分担することでおこる主張のわずかなずれはさておき、土壌微生物を育むことで私たちの健康が保たれるという視点は新しい。書評を思案しているときにすき焼きをいただいた。ファイトケミカルが豊富な春菊を食べて旨いと思うのは私だけではなかろう。これは植物とつきあってきた人類の性質のためなのであろうか。
