入門 食と農の人文学
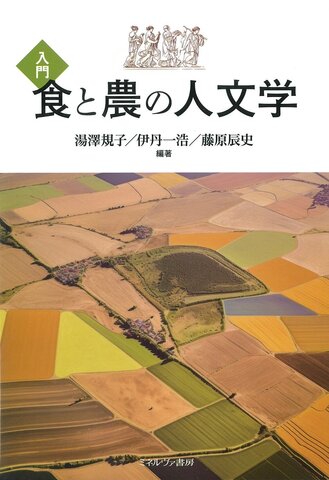
ー「食」をテーマにしていいものかと考えているアナタに読んで欲しい本ー
アジアの納豆文化の広がりについてのユニークな仕事をしている研究者は、かつて半導体のエンジニアで、海外青年協力隊員として、その地を訪れていた。そして、納豆と出会った。
マスコミ志望のアジア好きの学生は、フィリピンの大学院に留学して、ナマコから見えてくる世界に気付き、さらに捕鯨についてのあれこれ、油脂の問題に展開し、聞書等のユニークな仕事をまとめる研究者となった。
実際にジャーナリストとして働き、さらに金融やNPOで知見を深めた上で食糧政策の院生、教員となったという事例もある。
もとより、別の道から研究者となった、という話ばかりではない。インド近代史の研究を志し、インドの大学院に留学し、学生寮で美味しいとは言い難い食堂のご飯を食べ続ける中で、食という問題にも目を向けるようになったという経験談もある。
産業史研究から、織物工場の女性労働者の生活誌の資料から、食に関心を抱くようになり、あの名著を上梓するようになるというような話もある。
電車に乗って読み始め、気がつけば目的地を乗り越しそうなほど、没頭して、付箋をいっぱいにした興味深くも面白い本が、この『食と農の人文学』だった。
まあ、個人的には、二十人を越える著者のうち、半数以上は直接の面識があったり、あるいはその著書に触れいていたりというところだったのだけど、知っているとはいっても、そこまでの来歴経歴、志しまでは......というところで、余計に興味深く、ページを繰る手を止められなかったのだ。いや、付き合いのない研究者、ライターについても、なるほど、そのような仕事がと興味を覚えた。そこから、また、本を読んだ。
たとえば、あなたが何をテーマに、これから研究を、あるいは執筆をしようと考えているような立場であれば、無条件にこれを読むべし。なるほど、研究や調査の道はこのように広がっているのかと、目から鱗がぼろぼろ落ちる、はず。あるいは、食のような事象をテーマにしてよいものかと、悩んでいるような立場であれば、なおのこと。先輩たちが、どのようにして食や農のテーマと出会い、それを研究してきたかを詳細に語った本である。読んで損はない。そして、ヒントがいっぱいの、はず。
それなりの仕事を既に為してきたという世代にも読んでいただきたい。逞しい後輩たちが育ってきていると、安堵されるはず。
ま、つまりは食と農に関わる事象に興味が、関わりがあるどなたにもお薦めしたいという珍しい本であります。いや、本当はそれぞれについて、語りたいような内容なのだが、紙幅が......。
