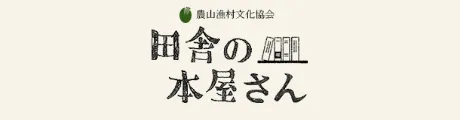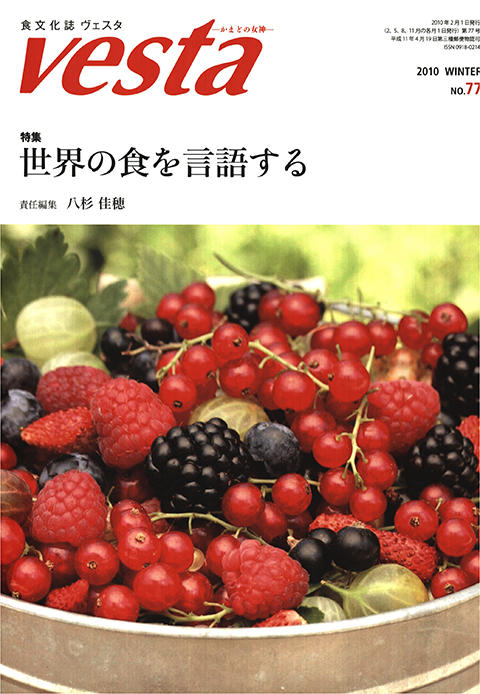
『vesta』77号
「世界の食を言語する」
2010.01.10
責任編集 八杉 佳穂(国立民族学博物館教授)
食はたいへん文化的なものであり、それぞれの文化を反映している。おおよそ人間が利用するものには名前がつき、食物を口にする行為は同じでも、環境が違い、民族が違うと表現が異なる。
4千とも7千ともいわれる世界の民族言語のうち、今回は20あまりを取り上げ、言語学者や人類学者たちに、その一端を紹介してもらう試みを行った。
こうした違いや多様性を豊かさと認めることこそ、21世紀の我々にとって、ポスト・グローバルの社会になればなるほど大切となるに違いない。
(巻頭言より)
食をことばする 八杉佳穂
アジア・極北編
食べるもの・飲むもの 藤代 節
稲作文化を守って生きる人びと、ムンダ人 長田俊樹
タミル語「食べる」の意味世界 山下博司
食べること、飲むこと、ご飯を炊くこと 阿良田麻里子
油がつむぐ豊かな関係 飯國有佳子
黒タイ語のキン(たべる・のむ) 樫永真佐夫
菜猪とよばれる中国のブタ 野林厚志
欧州・中東・アフリカ編
心も運ぶ“パンを焼く”動詞 庄司博史
ヨーグルトの言葉 マリア ヨトヴァ
古代シュメールの食 森 若葉
名もなき花と千のハシーシュ 菅瀬晶子
バカ・ピグミーの食と嗜好 林 耕次
ヤムイモの焼き加減をかたる人びと 金子守恵
テンボ族の「練り粥」 梶 茂樹
メリカ・オセアニア編
カナダ先住民の食とことば 笹間史子
ペルー・ケチュアの食 蝦名大助
コトバを食べる人びと 行木 敬
オーストラリア原住民の食と言葉 角田太作
フィジーのタロイモ 菊澤律子
多様なる世界をめぐって 八杉佳穂
〔レギュラー〕
昔話に見る食文化3 猿蟹合戦 石井正己
メディアと家庭料理④(最終回)ラジオの料理番組とローカル放送 村瀬敬子
大食軒酩酊の食文化6 ジャガイモのソーセージ 石毛直道
錦絵が語る食文化⑦ 浅草海苔 飯野亮一
食べる人たち 9 食と人の多様性 ゲスト・羽仁進/聞き手・宇田川 悟
文献紹介
奥村彪生著『日本めん食文化の1300年』 熊倉功夫