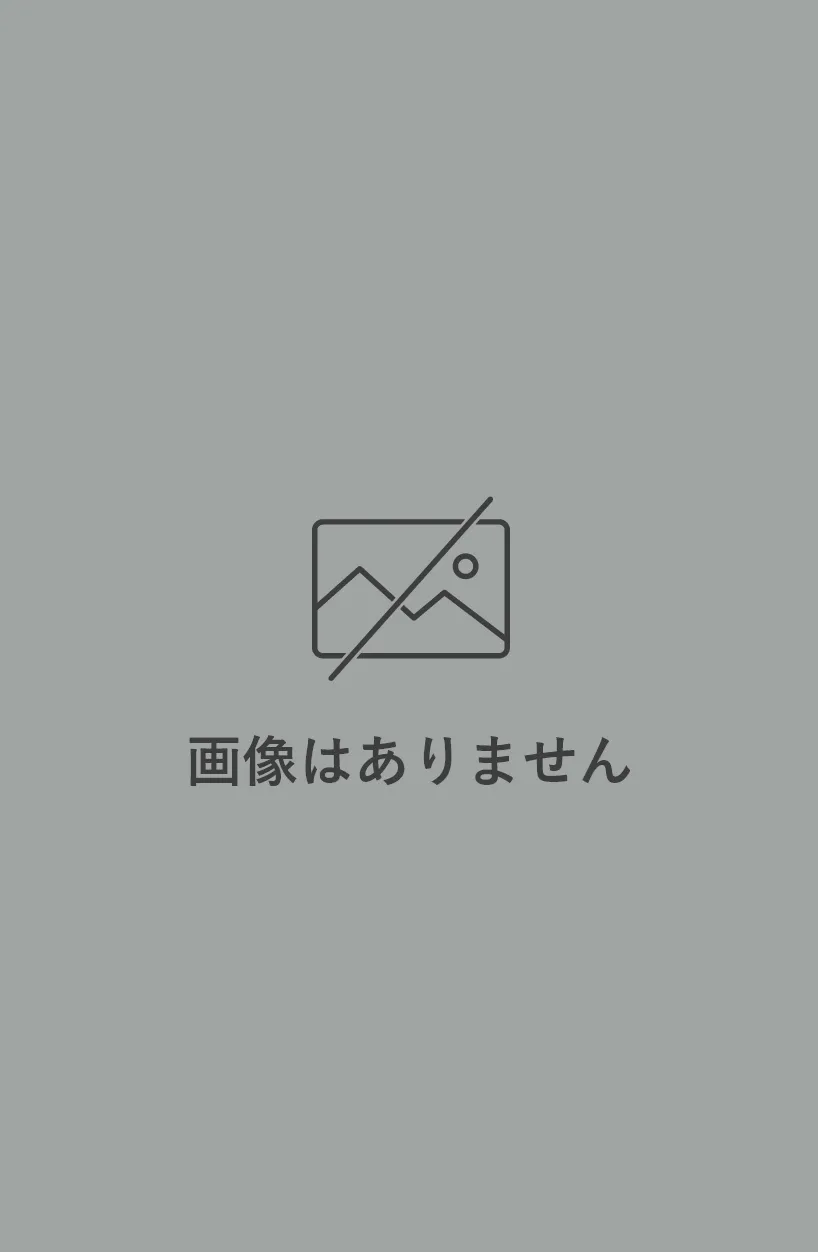沖縄黒糖の未来をデザインする
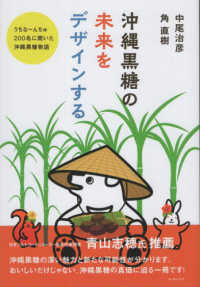
| 登録番号 | 057259 | 分類記号 | C3オ41 |
|---|---|---|---|
| 副書名 | うちなーんちゅ200名に聞いた沖縄黒糖物語 | ||
| 出版者 | ボーダーインク | ||
| 発行年 | 2024.11 | ||
| ページ数 | 189p | サイズ | 21cm |
| ISBN | 9784899824756 | ||
内容細目
食品 調味料 砂糖 黒糖 沖縄黒糖、その歴史 サトウキビの長い旅、たどりついた沖縄8島 (中尾) サトウキビ、その発祥 北インドからニューギニアへ サトウキビ、その文明の息吹 ニューギニアからインドガンジス川へ 西周り編 1 アレクサンドロス大王、イスラーム帝国の拡大 インド、中東、地中海 2 十字軍、大航海時代 ジブラルタル海峡、大西洋、そして新大陸 東周り編 ヨーロッパ列強のアジア侵略前夜 インドから中国へ 日本へ、食文化の発展 正倉院、出島、徳川吉宗 沖縄編 黒糖伝来 薩摩の琉球侵攻、そして沖縄黒糖誕生 沖縄黒糖の自由化 「琉球」から「沖縄」へ 3 開戦まで 2つの大戦とサトウキビ産業 4 復興、近代化 アメリカ世、琉球から再び日本へ そして現在 世界の中の沖縄黒糖、うちなーんちゅの黒糖意識 沖縄黒糖、そのおいしさ 歴史、食文化、科学からのアプローチ (角) そもそも、「おいしさ」とは何か? 黒糖の成分 違いは「非ショ糖成分」 黒糖と白糖の成分の違い 黒糖と白糖の製法の違い 黒糖以外の色のついた砂糖 世界の砂糖・黒糖利用の歴史と現在の利用法 ヨーロッパの甘味と砂糖文化の歴史 アジア・中南米の黒糖 日本(内地)の砂糖・黒糖利用の歴史と現在の利用法 甘味素材利用の歴史 奈良時代 室町時代まで 戦国時代 江戸 明治 戦前 黒糖利用商品の今 沖縄の砂糖・黒糖利用の歴史と現在の利用法 沖縄の黒糖「利用」の歴史はいつ生まれたか 沖縄で黒糖をどのように消費しているか 消費者調査結果 一口サイズをそのまま食べる お菓子としての使い方 料理としての使い方 飲料としての使い方 黒糖の新しい使い方 ビーガン料理 乳製品等との組み合わせ 黒糖の「においマスキング効果」をいかした使い方 黒糖のおいしさ要因と今後の使い方の発展 黒糖の味を決める成分 おいしさの化学的アプローチと高不か価値化のための提言 非ショ糖成分と味・香りの関係 黒糖の成分・味のばらつき要因 研究結果のまとめ 黒糖風味のばらつきに関する、ビジネス上の課題 課題解決のための研究の方向 研究結果のアウトプットイメージ 沖縄黒糖、その機能性 ぬちぐすいとして。黒糖力を検証する(中尾) まず「食の機能性」とは サトウキビ、そもそもが「ぬちぐすい」 古典の中の沖縄黒糖 砂糖が甘味王となり、沖縄戦では切なく悲しく 沖縄は黒糖研究のフロントランナー 現代の沖縄黒糖研究 バブル前夜、すでに先人ありき 20世紀、黒糖の母 21世紀、黒糖力の論理性 わずか5g、20kcalのパワー 黒糖を食べてストレス緩和 「黒糖力」その商品化デザイン まず規格化 機能性表示取得を目指して 継続的なコミュニケーション 沖縄黒糖、その社会的意義 社会にとって黒糖はなぜ必要なのか 環境を守る 地域を守る 国を守る 社会的意義の認知 沖縄黒糖、その未来戦略 6つの価値の見える化戦略(角・中尾) 戦略目標 黒糖戦略のステークホルダー 戦略の重要度 「6つの価値の見える化戦略」の実施内容 コク・香り 8島テロワール 抗ストレスとポリフェノール ミネラル 環境負荷が少ない 黒糖プロモーションのターゲット 対消費者(B to C) 対事業者(B B) 価値の「規格化」の重要性
カーリルは全国6,000以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に検索できるサービスです。