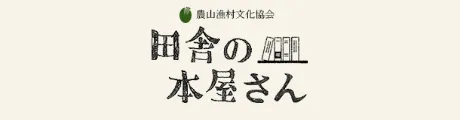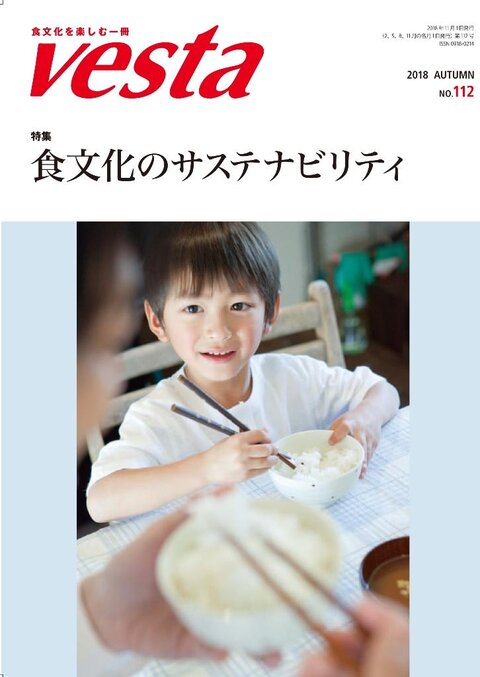
『vesta』112号
「食文化のサステナビリティ」
2018.10.12
特集アドバイザー 太田 心平(国立民族学博物館准教授、アメリカ自然史博物館上級研究員)
食文化の変化や継承については、本誌でもたびたび特集されてきた。「世界の食文化無形文化遺産」(101号)、「和食のクライテリア」(94号)、「変わりつづける『世界の食文化』」(74号)など。ただ、変化はその後も進んでいるし、継承という概念も琢磨されてきた。これまでと違う視点、より広い実践者の記事を交え、食文化のサステイナビリティ(持続可能性)を考えてみたい。
<特集>
Ⅰ 日本
1 地域
山形・庄内を食で元気に/奥田 政行
2 家庭料理
①手間はなんでも省きたい?
雑誌『オレンジページ』からみる家庭料理の昔と今/杉森 一広
②家庭料理は受け継がれているのか?/阿古 真理
3 流通
コンビニ食の変遷と未来/加藤 直美
4 和食文化持続のために
①食文化の継承と学校給食/伊藤 美穂
②(一社)和食文化国民会議が推進する和食文化の保護・継承活動/露久保 美夏
5 和食文化を海外に発信
①NHKが発信するJAPANESE FOOD/宮本 彩加
②築地市場で和食の謎解き/坂本 ゆかり
<TOPIC>鯨の味、恐竜の味
―進化とITは、嗜好の「持続」を断ち切るか?/藤本 憲一
Ⅱ 海外
1 フランス料理とサステナビリティ/八木 尚子
2 フランスの家庭食の伝統 ―サスティナブルの意味を考える/小坂 亜矢子
3 キムジャンが続くとき
―女性たちの協働から、家族行事、都市型イベントへ/太田 心平
4 あなたが中国で食べた天津煎餅餜子(ジェンビングオズ)は天津の煎餅餜子?/劉 征宇
5 変わる中東のコーヒー/菅瀬 晶子
まとめ 食文化のサステナビリティによせて/太田 心平
<連載>
幻の大衆魚:ニシンは山を越え、海を渡る/濵田 信吾
(第1回)北米先住民から学ぶサステイナブルな魚卵文化
大食軒酩酊の食文化/石毛 直道
(第42回)日振島のサツマ
すべての道は「食」に通ずる -イタリア-/宇田川 妙子
(第7回)トマトとイタリアの浅くて深い関係
嗜好品の文化論/髙田 公理
(第6回)現代世界の大都市における嗜好品
食でひもとく浮世絵の楽しみ(第2回)/林 綾野
文献紹介 旦部幸博著 『珈琲の世界史』/山内 秀文