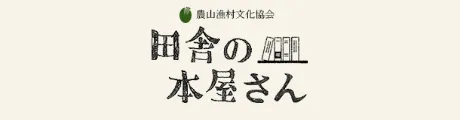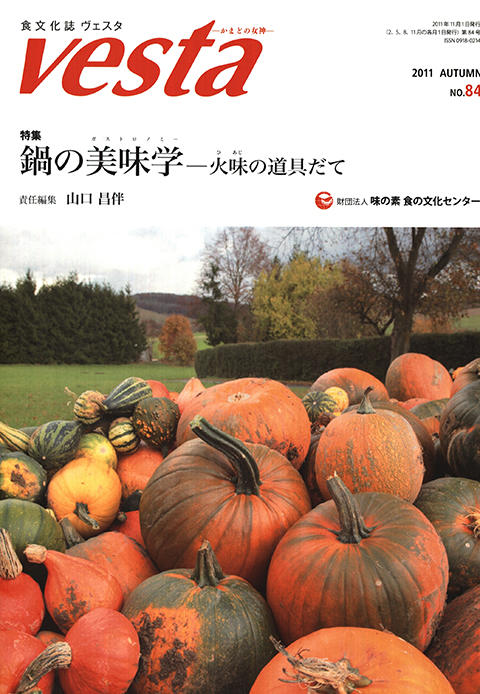
『vesta』84号
「鍋の美味学 ガストロノミー ―火味(ひあじ)の道具だて」
2011.10.10
責任編集 山口 昌伴(道具学会会長)
最近流行りのタジン鍋をはじめ、世界にはさまざまな形・用途の鍋がある。そして鍋の生み出す火味(ひあじ)(責任編集者造語:加熱活用によって生まれる味のバリエーション)の体系は、食文化という壮大な構築体の大黒柱に当る。自然環境、台所・かまど、そして民族の嗜好とともに鍋はどんな発展を遂げてきたのだろうか。調理道具としての鍋にスポットを当てて、世界各地の鍋や料理を紹介する。
(特集のねらい)
鍋仕立てとその使いぶり―各食文化圏比較の試み 文・イラスト 山口昌伴
〔鍋の美味学―火味の道具だて〕その用語法と執筆依頼について 山口昌伴
韓国の鍋、ネムビ(韓国) 金 桂淵
中国の鍋と料理 (中国) 西澤治彦
モンゴル草原の鍋(モンゴル) 石井智美
伝統を調理する器(インド) 小磯千尋・小磯 学
東南アジアの鍋―キッチンも中国とインドの間に(東南アジア) 森枝卓士
マグリブ地域のタジン鍋とクスクス鍋(マグリブ) 宮治美江子
北米(アメリカ)における鍋など調理器について(北米) 本間千枝子
土鍋にして名物のカピシャーバ料理あり(ブラジル) 田所清克
ヨーロッパの鍋(欧州) 舟田詠子
オセアニア、瓮の原点に迫る道具だて(オセアニア) 小林繁樹
対談 宇宙の食は地球の縮図!? 山口昌伴・畑中菜穂子
〔レギュラー〕
伝統を今に伝える2(最終回) 手火山式 鰹節製造 久田浩司
大食軒酩酊の食文化13「酒育談義」 石毛直道
食べる人たち16 「外交官の食卓」 ゲスト・松浦晃一郎/聞き手・宇田川 悟
狗肉の食とそのタブー(上)台湾「香肉」と犬肉食の分布 山田仁史
B級ご当地グルメの魅力3 「創出」 小林 哲
日本のワイン3(最終回) 世界に羽ばたく国産ワイン 柳田藤寿
民話に見る食10 「愚か村話」 石井正己)
文献紹介 野本 寛一編『食の民俗事典』 岩田三代