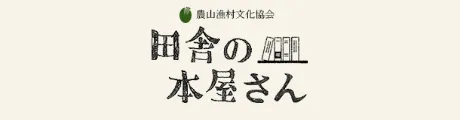『vesta』73号
「新「酒飯論」」
2009.01.10
責任編集 神崎 宣武(民俗学研究家)
米の飯、米の酒は、東アジアの伝統的な稲作地帯に広く分布して伝わっています。
そしてとくに日本では、稲魂(いなだま)信仰、お御酒(みき)をもっての直会(なおらい)や盃事(さかずきごと)など、そこに「精神性」を投じてきました。古代から現代まで、日本人が米(餅)と酒にどのような思いを持ち、かかわってきたかをご紹介します。
日本人にとっての飯と酒 神崎宣武
『酒飯論』とそれに続く上戸下戸論争 熊倉功夫
太平喜餅酒多多買(たいへいきもちさけたたかい)
律令官人の送別宴―餞酒(せんしゅ)について― 上野 誠
下戸は近畿、中部地方に多い 原田勝二
落語にみる上戸と下戸 山本志乃
ヒロインたちの酒~日本近代文学と女性の飲酒 佐伯順子
戦中・戦後の酒と飯~私のささやかな体験をもとに~ 石川松太郎
下戸も肴を好む 林 望
現代「酒飯論」
〔レギュラー〕
錦絵が語る食文化④ 新年の宴にみる散蓮華と酒器 飯野亮一
北タイのモチ食文化―消えゆく伝統菓子(カノム)を追って(下) 宇都宮由佳
食べる人たち⑥ 小山薫堂に聞く 宇田川 悟
大食軒酩酊の食文化3 ウクライナのサーロ 石毛直道
索餅の単位を解明する 奥村彪生
メディアと家庭料理①婦人雑誌と料理―「教養」から「実用」へ、「娯楽」としての食情報 村瀬敬子
文献紹介江原絢子・東四柳祥子著『近代料理書の世界』 前川健一