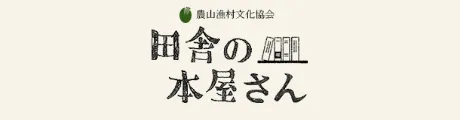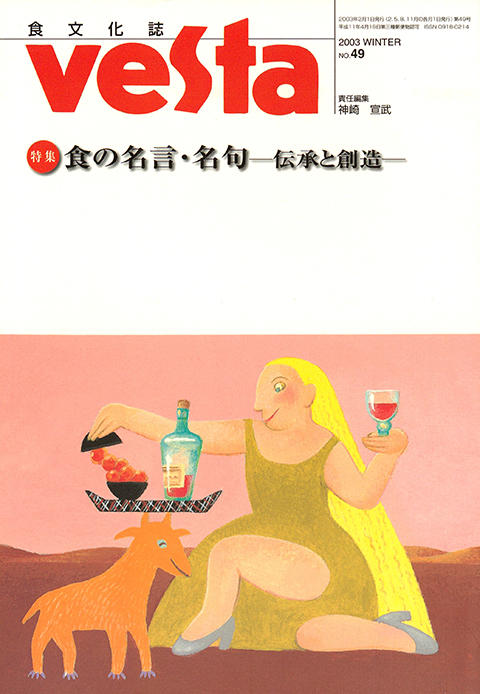
『vesta』49号
「食の名言・名句―伝承と創造」
2003.01.05
責任編集 神崎 宣武(民俗学者)
表紙画:奥山民枝
言葉は、生きている。
無論、長命な言葉と短命な言葉がある。前者の代表は、たとえば「腹八分目」。たとえば「医食同源」。言葉まわしはちがっても、それぞれの民族や地域が それを共有する。暴飲暴食をすすめる言葉なんかありはしない。ゆえに、それが長命なのである。程よく「食べあわせる」。それが食事の原則であろうことは、いうをまたない。たとえば「五味五色」。
なのに、このごろ、マスメディア中心の情報として、単品をとりあげ健康云々が喧伝される。日替わり健康食なんかありはしない。日々を程よく食べあわすしかないのだ。「しあわせは家族そろって三度食う飯」。その平凡さが尊いのである。
―責任編集者・巻頭言より―
カラー企画 世界の食の情景6・アメリカ「北カリフォルニアのある家族の食卓』 解説:有賀夏紀/写真:廣津秋義
ことばにみる食の伝承<日本> 神崎宣武
食に真理あり フランス人が飲み食べる 樺山紘一
北部カメルーン・フルベ族の伝統的食生活 江口一久
タイ/田に米あり、川に魚あり 山田 均
インド―ことわざにみる「浄・不浄」 小西正捷
韓国―漢字語にみる中国大伝統の継承様式 朝倉敏夫
座談会 「食の名言・名句あれこれ」 神崎宣武/堀内勝/本間千枝子/横澤彪
紀州・なれずし賛歌 梅田恵似子
欄外・酒のことわざ 『ヴェスタ』編集部
〔レギュラー〕
食から見た日本史 近代の食5 料理と食卓 高田公理
エッセイ 動きと、おしゃれと、自由と―これからの食文化― 木村尚三郎
野生食を訪ねて・6 野鳥フィールド・ノート 小山修三・岡野洋子・金子裕之
飛騨高山の食―宴会の祝い歌「めでた」の役割 田中 彰
食と倫理1 「失われた倫理を求めて」 山口裕之
ローマ時代の食とモルタリウム―開花した擂鉢(すりばち)文化― 荻野繁春
文献紹介 ヨーロッパ食文化研究のために⑭ 『マーケティングと現代性』 カタジーナ・チフィエルトカ
取材 食の学習現場から 棚田を活かした総合学習 ―徳島県・上勝小学校の取り組み― 草野美保
文献紹介 矢谷慈國/山本博史 編『「食」の人間学』 熊倉功夫